
目次
はじめに
デジタル・トランスフォーメーションとは?
DXによって保健活動にはどんな変化が起こる?
最善のケアが提供されているか?
保健師の質の高いケアを提供する体制整備とは?
本研究のねらい
各研究班の詳細
研究班体制
はじめに
わが国は狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、未来社会(Society5.0)に向けて変革期を迎えています。私たちの研究チームでは、この変革期に保健師活動がどのような影響を受けるのか、未来を見据えた保健師活動の今後のあり方を考えています。本ページでは、まずデジタルトランスフォーメーションについて理解を深め、保健師活動がどう変わるのかを考えてみたいと思います。
デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは?
まず、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)について簡単に説明します。DX とは、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させることです。つまり、単にアナログデータをデジタルデータにするだけではなく、「人々の生活を良い方向に変
化させること」が重要です。
図1 は組織におけるDX の構造を示しています。DX には、デジタイゼーション、デジタライゼーションが含まれます。
デジタイゼーションはアナログ・物理データのデジタルデータ化です。保健師活動で言うとケース記録や活動統計のデジタルデータ化が当たります。
次に、デジタライゼーションは個別業務プロセスのデジタル化です。例えばデジタル化したケース記録を活用することで訪問時期を逃さないように管理したり、デジタルデータを活用して地区診断を行うことが当たります。
そして、DX は、これらのデジタイゼーション、デジタライゼーションを基盤とした、組織横断的な業務プロセスのデジタル化であり、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの改革と言われています。保健師活動で言えば、ケース記録のデジタル化等により業務を効率化し、生み出した時間で訪問時間を増やしたり新規事業を立上げたりするといったことが考えられます。
DXによって保健活動にはどんな変化が起こる?
アナログデータのデジタル化であるデジタイゼーションが進むことで、住民の方々の健康に関するデータや専門職の支援に関するデータが共有、見える化されるようになります。
また、デジタル技術を使って業務プロセスを見直すデジタライゼーションが進むことで業務の効率化・コストカットが可能となり、生み出した時間や資源で質の高いサービスを提供することが可能になります。
つまり、DXによって業務が効率化し、保健師活動に時間を使うことができるという効果が期待できる一方で、保健師の専門性や活動の質が問われる時代がやってくることとなり、今後PDCAサイクルを回すことによって、根拠を持って質の高いサービスを提供することが一層重要になると言えます。
そこで保健師としては、デジタル化の波を活用することにより、保健師活動には住民の方々にどんなサービスを提供していて、どんな効果があるのか、そのPDCAを回すことができる仕組みを意図的に構築していく必要があると考えています。

最善のケアが提供されているか?
保健師は日々、自身の専門性を活かしながら対象者の価値観や希望、地域特性等に合わせたケアを行っています。限られた資源を活用しながら住民の健康増進や疾病予防という成果を最大限生み出すためには、過去の保健師活動に関するデータやエビデンスに基づき、最適なケアを選択できることが望ましいと考えます。例えば、母子保健活動を行う上で、①母親の抑うつ(状態A)に対して、データやエビデンスに基づいて、想定されるケアの選択肢(ケアA・ケアB)から、望ましいケアを選択できる。②選択したケア(例えば訪問)を行った後の母親の抑うつ(状態AA・状態AB)について、データに基づいて評価できる。③ ①、②を通して、保健師活動のデータ(個人に紐づいたケアA・ケアB(行為データ)と状態AA・状態BB(観察データ))を常に蓄積・分析する。これらが実現できれば、データに基づき実践のPDCAサイクルを回し、保健師活動の高度化・効率化が図れると考えています。加えて、エビデンスに基づく活動は、政策決定者への提言にも役立ち、地域全体の健康づくりに貢献します。

保健師の質の高いケアを提供する体制整備とは?
保健師が質の高いケアを提供するためには、日々の活動をデータとして蓄積し、そのプロセスやアウトプット、アウトカムを評価するシステムが必要です。しかしながら、現状ではケアの質を担保するためのプロセスを可視化する仕組みや、ケアを測定するための指標、記録する際の用語の標準化ができていないことが課題です。用語の標準化に関する課題は、例えば保健師が同じ妊婦さんを面接した際、お母さんの様子をある保健師は「不安な様子」と記録し、別の保健師は「心配事が多い」と記載するなど表現の揺らぎがあることを指します。それらの課題を解決するためには保健師活動のパス作成、用語の定義と標準化、ICT活用による持続的な量的・質的データ収集、分析可能なシステム構築が必要です。

本研究のねらい
これまで述べてきた課題に対応すべく、本研究では、ICT活用による保健師活動評価手法の標準化および、PDCAサイクルに基づく保健師活動の推進を目的とし、下記の3つの研究班で研究を進めています。
研究①保健師活動評価指標の体系化と評価手法の検討
研究②ICTを活用した保健師活動マネジメントツールの開発
研究③保健師のICT及び保健師活動のマネジメントスキル向上プログラムの開発

各研究班の詳細
研究班体制
厚生労働科学研究(健康安全・健康危機管理対策総合研究事業)
令和4―6年度「ICT活用による保健師活動評価手法の開発及びPDCAサイクル推進に資する研究」
研究代表者
| 田口 敦子 | 慶應義塾大学看護医療学部 地域看護学分野 教授 |
研究分担者
| 村嶋 幸代 | 湘南医療大学大学院・保健医療学研究科・教授 |
| 春山 早苗 | 自治医科大学・看護学部・教授 |
| 水流 聡子 | 東京大学・工学系研究科・特任教授 |
| 杉山 大典 | 慶應義塾大学・看護医療学部・教授 |
| 赤塚 永貴 | 横浜市立大学・医学部看護学科・助教 |
| 加藤 由希子 | 慶應義塾大学・看護医療学部・助教 |
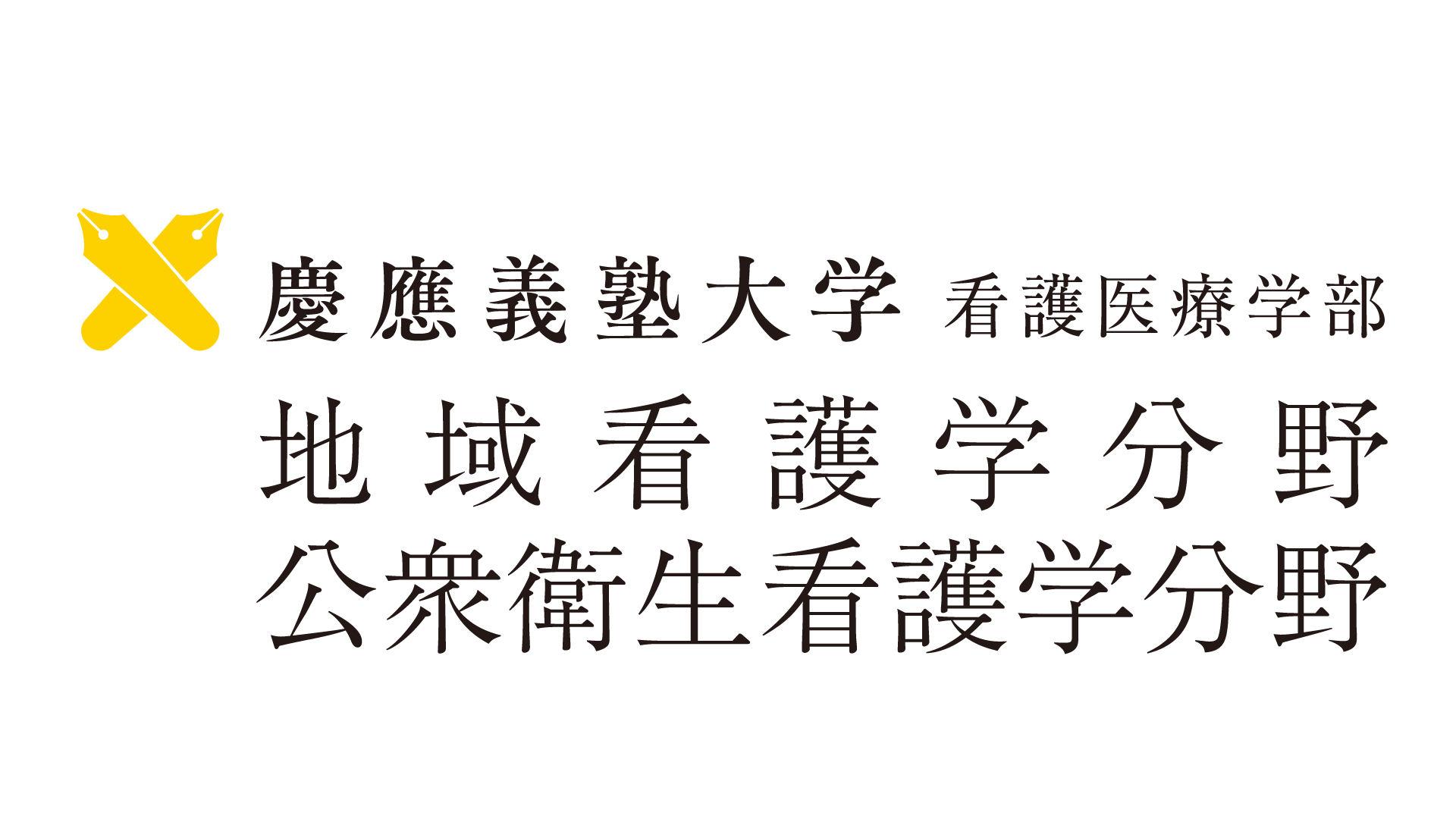
 研究班1 保健師活動評価指標の体系化と評価手法の検討
研究班1 保健師活動評価指標の体系化と評価手法の検討 研究班3 保健師のICT及び保健師活動マネジメントスキルの向上プログラム開発
研究班3 保健師のICT及び保健師活動マネジメントスキルの向上プログラム開発
